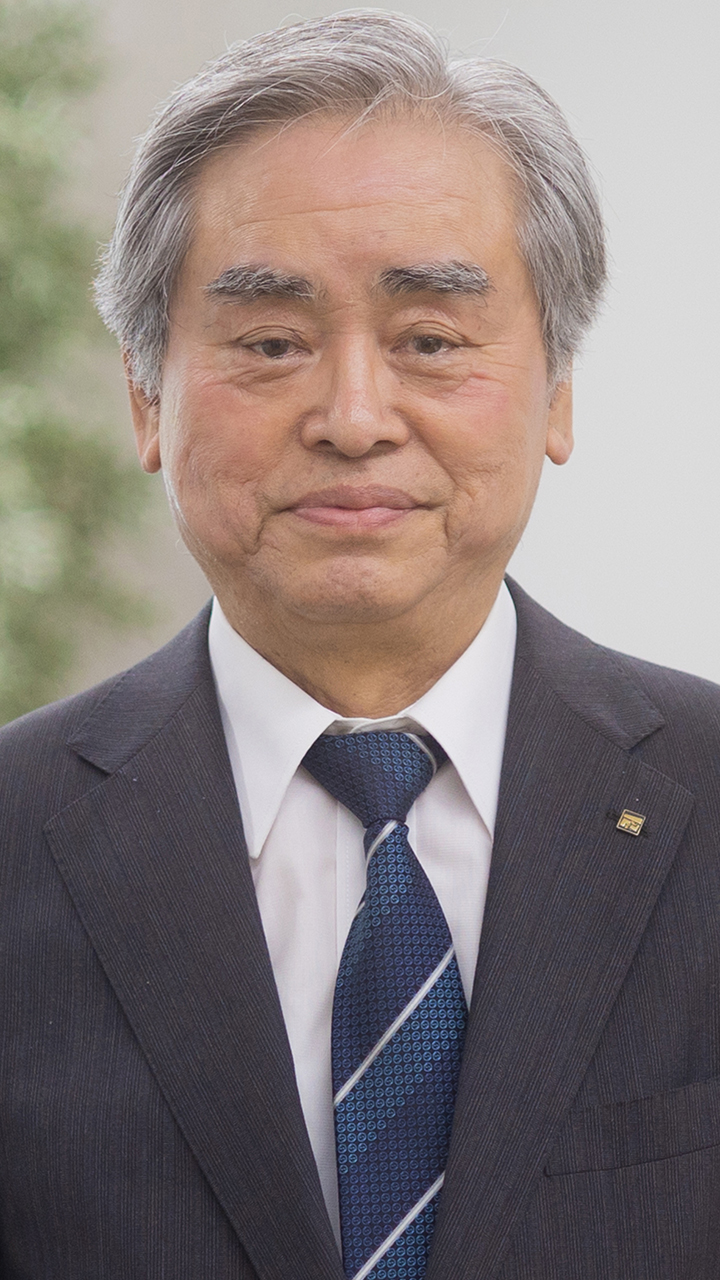インタビュアーの視点 – 志摩市民病院|江角悠太氏
志摩市民病院は、三重県志摩市大王町波切に位置する、病床数60床の小さな公立病院です。院長の江角悠太氏(当時)は、学生時代から「世界平和」を人生のテーマに掲げ、すべての人が幸せになるために貢献できる場所として、この病院を選びました。
地域医療が直面する構造的課題
日本の医療市場は約46兆円の規模を有し、地域医療機関(病床数200床未満)は約5,000施設存在します。しかし、地域医療機関の約30%が赤字経営に陥り、特に病床数60床以下の小規模病院の存続が困難な状況にあります。診療報酬の削減と人件費の上昇により経営は圧迫され、地域医療機関の医師不足率は約40%に達しています。
2025年に団塊世代が75歳以上となり、後期高齢者医療の需要が急増する一方、慢性疾患の増加や複数疾患の併存が増加しています。医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築が急務となる中、地域医療機関の役割はますます重要になっています。
志摩市は、三重県の東部、志摩半島に位置し、人口約50,000人、高齢化率約35%と全国平均より高い地域です。名古屋都市圏から約100km、大阪都市圏から約150kmの距離にあり、地域完結型の医療が求められています。志摩市民病院は、この地域唯一の公立病院として、地域医療の最後の砦としての役割を担っています。
存在意義を見いだせなかった日々
江角氏がこの病院に入った7年前、病院は経営難の真っ只中にありました。専門科に固執した受け入れ態勢によって地域住民からの信頼を失い、患者数は減少。スタッフが懸命に働いても住民からの評判は上がらず、「診療所にしてはどうか」という声さえ上がっていました。
江角氏自身も、自らの存在意義を見いだせない日々を過ごしていました。世界平和を実現したいと思って来たのに、何もできない。変えたい、何とかしたいという想いが空回りする毎日。存在意義が全く見いだせない状態が続きました。
転機となった存続危機
転機は、他の医師が次々と辞めていき、病院が存続不能になりかけた時でした。
「この地域のために入ると決めてきているので、僕が辞める理由はなかった」
江角氏は一人残ることを選びました。その決断が、職員たちの「残ってほしい」という想いを引き出し、ようやく自らの存在意義を見いだすことができたといいます。
最初は、自分の力を過信しているのではないかという迷いもありました。本当にこの病院は必要なのか。住民説明会を開き、直接聞きに行きました。ほぼ全員から「いらない」と言われるかもしれないという覚悟もあった。しかし、地元の人たちは「必要だ」と言ってくれました。この声が、江角氏の自信につながりました。
暗闘の中でも、懐中電灯を持って何とか道を探そうとしていた職員が何名かいた——その存在もまた、大きな支えになったと江角氏は振り返ります。
病院まつりという決意表明
「裸一貫、最初から始める」
その決意を住民に伝えるため、病院まつりを開催しました。何よりも、働いているスタッフの顔を知ってもらうこと。雰囲気、声、どんな想いで働いているかを正直に伝えること。
その日の活気に、スタッフ自身も驚いたといいます。この病院にこれだけのことができるのか、と。
医療だけでは人は幸せになれない。すべての人の協力が必要です。一対一の関係を超えた関係を作らない限り、日常生活の中に病院が、生活の中に医療があるということは実現できません。
「絶対に断らない。」という基本理念
こうして確立されたのが、「絶対に断らない。」という基本理念です。
診療科にとらわれず横断的に医療を行う総合診療のもと、病院が提供したい医療ではなく、患者がやってほしい医療を大切にする。地域包括ケアの中核を担う病院として、なるべく地元で問題を解決し、患者が安心して自宅に帰れることを目指す。
地域の問題の6〜7割は志摩市民病院で解決し、手術や高度な治療が必要な2〜3割は大きな病院へ紹介する。早めに気づき、早めに入院し、早めに治療すれば、すぐに帰れる。近くにいる介護スタッフや医療従事者と連携して、地元で良い生活を送れるようにする。
他の医療機関がなかなか対応しにくい不採算部門——緩和医療、終末期医療、認知症医療なども積極的に受け入れています。小規模だからこその機動性を生かし、一人ひとりのニーズに合わせたオーダーメイドの医療を提供できる。それが志摩市民病院の強みです。
研修医時代の原体験
江角氏の医療観を決定的に変えた出来事があります。研修2年目のこと。70代の寝たきりの患者さんを担当しました。2回心臓が止まった経験があり、肺炎で入院してきた重症の方でした。
家族の要望で心臓マッサージを続けましたが、やればやるほど患者の体を傷つけてしまう。それでも手を止めることができない。家族が「やってくれ」と言っている以上、止められない。
息子さんは「隣の島にいる妹に会わせたい」と言い、妹さんが来るまで続けてほしいと一点張りでした。その晩に亡くなるはずだった患者さんは、翌朝まで持ちこたえました。
妹さんが来た瞬間、「お母さん、お母さん」と声をかけた。意識もない、会話もできない、寝たきりで天井しか見られない人が、両目から涙を流した。その10秒後、心臓が止まりました。
「それを見た時、まったく本人の意志を聞こうとしていなかった自分が最悪の医者だった、と気づきました」
言葉として聞くことはできなくても、聞こうとしていなかった。この人はどう思っているのか、どうしたいのか。心臓が止まった後のことだけを考え、止まるまでの本人がどうしたらより幸せになるかを考えようとしていなかった。
「あの人がきっかけです。僕らがやりたい医療ではなくて、患者さんがやってほしい医療を突き詰める——それをあの人が教えてくれました」
患者の人生の中に答えがある
認知症の方であっても、そこに彼・彼女は生きていて、考えることができる。認知症とともにどう生きたいのか、どう死んでいきたいのか。その意思は尊重されるべきだと江角氏は語ります。
今まで生きてきた人生の中に答えがある。だから会話を重ねる。家族の話、仕事の話、思い出話。その中に、これからの10年をどう生きたいかの答えがある。「幸せですか」と聞く。幸せじゃなかったら、何が幸せじゃないのか、そこから掘り下げていく。
「たとえ設備が少なくても、たとえできることが少なくても、家の近くにあるこの病院で、今まで診てくれたあなたに最後をお願いしたい」
そう言ってくれる患者さんが増えてきている。それは、病院の職員が、一人ひとりの患者さんと信頼関係を築いてきた証だと江角氏は感じています。
地方から日本の医療を変える
「病気を治すやり方しか教わっていないんですよ。治せなくなった人の救い方は教わっていない」
だから医療者は、自分たちがやりたい医療をやりがちになる。しかし本来、医療は患者がやってほしい医療を提供するべきもの。今の日本の諸問題は、患者さん一人ひとりの中に集約されている。その人の社会的背景や考え方を含めて治療する——その医療の考え方を、志摩市民病院は実践しています。
「世界平和までは、僕が生きている間には難しいかもしれない。でも、高齢者になっても、死ぬ間際になっても、みんな幸せだよと言える日本にしたい」
高齢者が明るければ、子供たちも明るくなる。「いずれ自分も年寄りになる」と暗い気持ちになれば、誰も子供を産まなくなる。人生最後の10年を明るく過ごせる社会を作ることが、全世界にとって必要だと江角氏は語ります。
アストライドのミッション
志摩市民病院の「絶対に断らない。」という基本理念。その根底にあるのは、「患者がやってほしい医療を突き詰める」という江角氏の医療観です。
研修医時代、意識のない患者さんが妹との再会の瞬間に涙を流し、10秒後に息を引き取った——あの経験が、江角氏の医療観を決定的に変えました。「病院がやりたい医療」ではなく「患者がやってほしい医療」。この転換は、単なる方法論の違いではありません。患者の人生そのものに向き合う覚悟の違いです。
経営難の中、医師が次々と辞めていく状況でも一人残り、「この地域のために」と決意した江角氏。住民説明会で「必要だ」という声を聞き、病院まつりで「裸一貫、最初から始める」と決意表明した江角氏。その想いは、数字では測れない価値を持っています。
私はこれまで、200社以上の経営者インタビューに携わる中で、こうした経営者の想いに向き合ってきました。地方の小さな病院から「日本は高齢者になってもみんな幸せだよ」という未来を目指す——その志は、地域医療の課題に直面するすべての人にとって、希望となりうるものです。
経営者の言葉には、その人が歩んできた道のりと、これから歩もうとする道筋が刻まれています。江角悠太氏の言葉もまた、志摩市という地域の医療を支える覚悟と、日本の医療を変えようとする志として、この映像の中に残されています。
記事を書いた人

アストライド代表 纐纈 智英
アストライド代表。前職を含め地域企業を中心とした200社以上の経営者インタビュー映像を制作。現在は「左脳と右脳のハイブリッド」を掲げ、戦略設計から映像・Web・各種コンテンツ制作まで手がける。 これまで音楽家として楽曲提供、行政職員として12年間 制度運用・予算編成等に従事。その後、NPO法人、映像・マーケティング分野に転じ、現在に至る。現在は大学非常勤講師として映像編集ソフトの操作指導も行う。